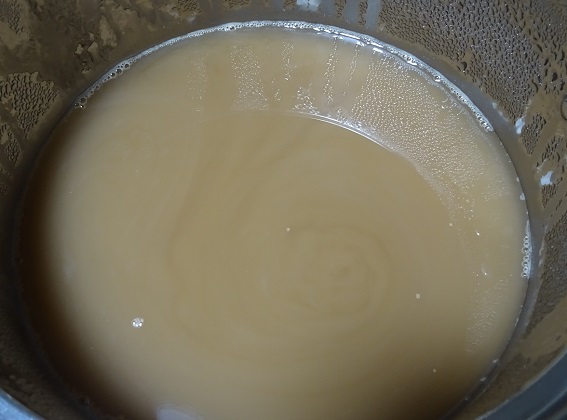あく巻き
2024/6
昨年は草木灰汁であくまきを作ったため、餅米が溶けずに失敗してしまった。今年はよもぎ灰汁であくまきに挑戦してみる。
【材料・分量】
○ 餅米…700g
○ よもぎ灰汁…400cc
○ 水…400cc
○ 竹皮…真竹の皮:8枚
餅米700gを洗ってからよもぎ灰汁400ccと水400ccを混ぜたものに一晩つけておく。

翌日見てみると米が黄色くなっていて、よもぎ灰汁を濃く煮だしていた為アルカリ成分がしっかりしていると感じる。
餅米の水を切った後(漬け水は茹でる時に使う)、竹の皮に詰めて3時間ほど鍋で茹でる。漬け水だけでは足りないのであくまきが浸かるように水分を足す。

自然冷却させた後に冷蔵庫に入れて保存する。いくら殺菌されているといえども常温では悪くなる気がする。

翌日、畑に持って行って食べてみたら米がしっかりと溶け切っていること、臭みと若干の苦味がまさしくあくまきであった。よもぎ灰汁の有用性がよく分かった次第である。
2017/9
【材料・分量】(あくまき3個分…のはずでした)
木灰汁製作と餅米を浸すのに1日、翌日にあく巻き製作をするので2日間と見積もります
○ 餅米…500g
○ 木灰…200g
○ お湯…4cup
○ 竹皮…孟宗竹の皮:3枚
《予定外の材料》
○ みょうがの生皮…20枚ほど
※ 画像クリックで拡大が見れます

鹿児島旅行(2017年05月)で購入した木灰をやっと使う時が来ました。重い腰をあげての「あく巻き」挑戦です。
地元の市場の東吉野(仮名)さんが木灰で作った蒟蒻を売りに来ていた事があり、これが今回の木灰の購入意欲の下地になっています。改めて木灰のことを話してみると
「何の木の灰なの?あ、判らないんやね?」
「ケヤキは木灰に向かないと聞くねんけど」
と教えてくれました。
あく巻きには興味津々のようで上手に作れたらお裾分けしたいと思います。
そして、使った木灰は、鹿児島県曽於市大隅町にある「(株)津曲食品」さんのものです。

木灰は思った以上に、砂のような粗い粒子がかなり混じっていました。木灰から木灰汁を作りたいのですが、いかんせん、ネットでは「あく巻きの作り方」はあっても「木灰汁の作り方」はあまり載っていないのです。
ともかくも、珈琲のように、少量ずつお湯を入れて時間をかけて落としていくことがポイントのようだと解釈しましたので、サラシと洗濯ばさみと鍋を用意しました。

小麦粉のように舞い上がる細かい粒子も入っているので、サラシが目詰まりを起こしてしまい、なかなか落ちていきません。ネットでは、タオルを敷き、その上を濡らした木灰を鍋状に築き上げて、注いだお湯の勢いで穴が開いてしまわないよう静かに落としていく方法を紹介していた人もいました。なるほどなぁ…一理あります。
結局、スプーンでかき混ぜながら落としていきました。
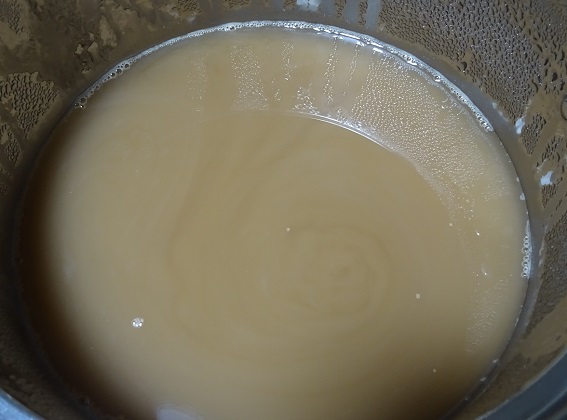
木灰汁ができました。かなりの強アルカリ性なので、舐めてみるとピリピリ舌がしびれます。香りのない山椒を舌に乗せしたら、こんな感じになるのではなかろうか、などとあえて説明するならこんな感じ。
溶かしてしまうので、ビニールやアルミ系の道具は厳禁。手がぬるぬるするのも、アルカリ性だからなんだそうです(東吉野(仮名)さん談)。やってみて初めて判ることもたくさんありますよね。
まだ濁っていますので、もう一度、サラシで濾します。

泥と化した細かい粒子が現れました。なかなか落ちていかないので、スプーンでかき混ぜつつ、キリのいいところで濾し終えます。(てきとーですみません)これで木灰汁のできあがりです。

あらかじめ洗っておいた餅米を、木灰汁に一晩漬けておきます。
それとともに、竹の皮も水に漬けておきます。鹿児島旅行のあと、あく巻き用にと思って近所の竹林で拾った3枚の竹の皮があるので、それを使いました。竹の皮が3枚しかないものですから(こちらはスーパーに竹皮が置いていないのが普通の奈良県なので、購入は難しい)、3枚基準の分量で餅米も木灰もすべて計りました。

翌日。
餅米をザルにあげて水気を切ります。濾しきれなかった木灰のカス(?)も付着してしまっています。木灰汁で洗い流してどうにか綺麗にしました。木灰汁は後で煮る時に使うので大切に取っておきましょう。

餅米が木灰汁で黄色く変色しています。包み用の竹皮までもが黄色いシミができています。よっぽどの強烈さなんでしょうねえ。
まずは、竹皮のお手入れです。水に漬けた竹皮を綺麗に水洗いして拭き取り、紐用に両端から2,3本ずつ切り取っていきます。切り取ったら、てっぺんのトンガリを切り抜きます。
それから、最初は、大さじ大盛り1杯分くらいの餅米を竹皮に乗せます。

竹皮の包みの形を整えます。この時点ではまだ縛りません。

口から餅米を入れていきます。
トントンと底を叩きながら、餅米をびっしりと…えぇ、びっしりと入れていきます。

バンバンになった竹皮を竹紐で縛ります。すごいでしょう、このびっしり感。
こぼれないよう、竹紐もしっかりびっしりと縛りました。えぇ、縛りましたとも。

いかがでしょうか。この立派なあく巻き3兄弟。
竹皮3枚を基準に分量を計ったのに、餅米が余ってしまいました。びっしり詰めたにもかかわらずに、です。
もう一度、ホームページで分量を確認しましたところ、過ちに気がついたのです。
我々の拾った竹皮がかなり小さかったという過ちに。
孟宗竹の皮のはずなんですが、鹿児島の竹は育ちが違うんですといったところなのでしょうか。もっと拾っておけば良かった…と後悔しても仕方がありません。ここは早急に別の打開策を打たなければなりません。

真っ先に頭に浮かんだのが、和菓子を包む笹。しかし、笹を取りに行くのは面倒くさい。笹に似たもので何か無いだろうか、ビニールでは駄目だ…次に頭に浮かんだのが、ベランダで栽培している「ミョウガ」です。
それしかない!
2枚で1セット×10セット=20枚 かなりの数の葉っぱを切りました。密生しすぎていたのでミョウガもこれですっきり、我々もあく巻きが作れるということで一石二鳥でした。
ありがとう、我が家のミョウガ。

ミョウガで餅米を包むことはなかなか難しく、輪ゴムで仮留めしてから入れていって包み、最後にタコ糸でぐるぐる巻きにすると作りやすかったです。ミョウガの葉は食べてもおいしいので(ただし春限定で)、食用包みにしても問題はないと思います。

木灰汁を入れた鍋に、包んだあく巻きを入れていきます。ひたひたにならなかったら、水を足します。
私は考えていなかったのですが、鍋の大きさを考えて包みあげた時のあく巻きの大きさを調整することも重要だったのかもしれません。鍋いっぱいいっぱいの大きさのあく巻き3本だったので、残りが小さなミョウガ葉包みじゃなかったら、入りきらなかったかも…。

3時間弱火で煮込みます。随時、様子を見て差し水をしていきます。
すっかり落し蓋が木灰だらけになってしまいました。

完成しました!みょうが葉巻きのあく巻きです。ぎゅうぎゅう入れすぎて、膨らんだ餅米を包み込み切れず、破裂してしまっています。

こちらの竹皮版あく巻きも、破裂してしまいました。餅米をびっしり入れてはいけない。ぎっしり縛ってもいけない。これがあく巻き作りにおける教訓です。
これもすべて竹皮が3枚しかなかったことに起因する、失敗です。3枚を基準にしちゃあいけなかったんですよ。分量が先にあるべきだったと私は考えています。

お味のほうはとてもうまくいきました。もしかしたら鹿児島で買ったあく巻きよりもおいしいかもしれません(自分で作ったものって、どうしてもそうなっちゃいますよね)。あんなに苦手だった木灰汁からくるえぐみが、くせになりそう…とまで思ってしまいました。
破裂したことにより、水分を吸いすぎたせいでフニャフニャになったので、冷蔵庫に1晩寝かせてみたところ、ちょうどいい堅さになりました。一方、みょうが葉版あく巻きは、恐ろしくて画像は載せられませんが、ミョウガの葉の色が移ってしまった上に細長かったので、なにかの軟体動物のような「モノ」に見えてしようがないのです。
● あくまきを食べた感想
- 砂糖: えぐみが強く出るのであくまきが本当に好きな人向け
- 黒糖: えぐみがかなり消えて甘ーい食べ物に変身
- 醤油: えぐみがほぼ感じられなくなってコンニャクのような食感を楽しめます
- 砂糖醤油: 醤油だけだとえぐみ消えるけども砂糖でえぐみ復活
- わさび醤油: わさびのピリピリ感が加わってよりおかずっぽくなりました
● 最後に
- 竹皮の偉大さを思い知りました。ああいう素材を、化学であれ石油であれ人間は作り出せるだろうか。いや作り出せはしまい。自然の賜物で、熱にも溶けない、餅もあまりくっつかない、それでいて木灰の味はしっかり染み込ませるというすごい素材なのだと、今回、竹皮不足によって思い知らされました。もしかしたら応用編はもっとあるかもしれません。来年の春はもっと竹皮を拾ってきて生活に導入していきたいと思いました。
- 昔は、囲炉裏や竈など熱エネルギーは薪だったので、木灰がよく取れたらしいです。木灰から作った汁は殺菌能力・洗浄能力・保存能力も高く、保存食の製造や洗剤などに使われていたのだそうです。薪から電力へとエネルギー源が変わったことにより、失われたもっともたるものが木灰なのかもしれません。
料理に戻る
TOPへ戻る